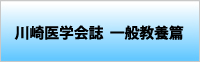2016.10.11
A pregnant woman with appendiceal diverticulitis who was preoperatively diagnosed by ultrasound in the second trimester: A case report
虫垂憩室炎は比較的稀な疾患であり,急性虫垂炎と比べ,穿孔率が高いがその術前診断は難しい.体外式腹部超音波検査で術前に診断した虫垂憩室炎の1症例を経験したので,文献的考察を加えて報告する. 症例は24歳,妊娠25週5日の女性.腹痛を主訴に近医を受診したところ,急性虫垂炎の疑いで当院へ紹介受診となった.体外式腹部超音波検査で,虫垂憩室炎と診断し,緊急手術となった.切除標本の病理学的検査により,虫垂憩室炎と確定診断された.doi:10.11482/KMJ-J42(2)159 (平成28年9月16日受理)
2016.10.11
Takayasu arteritis concerning the superior mesenteric artery:A case report
腹痛を呈した上腸間膜動脈(superior mesenteric artery: SMA)に限局した高安動脈炎の一例を経験したので,文献的考察を加えて報告する.症例は17歳,男性.心窩部痛・右背部痛を認め,近医を受診し,その際施行した体外式腹部超音波検査(ultrasound: US)でSMA の壁肥厚が疑われ,当院総合診療科を紹介受診した.身体診察では上腹部正中に軽度圧痛を認め,血液生化学検査では血沈(60min)35mm, CRP 3.92mg/dL と軽度上昇を認めた.US では,腹痛を訴える部位に一致してSMA 起始部にびまん性の壁肥厚を認め,血管炎が疑われた.胸部造影・上腹骨盤部単純造影CT 検査(computed tomography: CT)ではSMA 周囲に造影効果を認める軟部影を認め,18F-FDGPET(18F-fluorodeoxyglucose positron emission tomography: PET)/CT 検査ではSMA 起始部付近に腫大と軽度のFDG 集積を認め,動脈炎による集積で矛盾しない所見であった.以上のことから,SMA に限局した高安動脈炎と診断した.ステロイド治療を開始し腹痛は速やかに消褪すると共に,US 所見にも改善がみられた.doi:10.11482/KMJ-J42(2)151 (平成28年9月7日受理)
2016.10.11
A case of small solid pseudopapillary neoplasm with atypical appearance
症例は37歳,男性.直腸癌の術前精査のために行った腹部造影Computed Tomography(CT)検査で,膵尾部に径15mm の遅延性濃染を示す充実性腫瘤を認めた.腹部エコー検査で辺縁不明瞭であったため,腫瘤は被膜を形成していないと思われた.Fluorodeoxyglucose-Positron EmissionTomography / CT ではhot spot として描出されたため,膵管癌が疑われた.診断確定のために行った超音波内視鏡ガイド下穿刺吸引組織診ではSolid Pseudopapillary Neoplasm (SPN)であったため,脾温存膵尾部切除術を施行した.術後の病理学的検査所見では,腫瘤は被膜を有さず,周囲膵組織への浸潤もなく,悪性所見は認めなかった.被膜を有さない小型な非典型例のSPN を経験したので,若干の文献的考察を含めて報告する.doi:10.11482/KMJ-J42(2)143 (平成28年8月25日受理)
2016.10.11
Newly developed morphological analysis of the olfactory bulb neural circuit using the synaptic markers, VGLUT1 and VGAT.
嗅覚の一次中枢である嗅球の投射ニューロン(僧帽細胞,房飾細胞)は,その樹状突起上で樹状突起間シナプスを形成したのちに,高次の脳中枢に情報を伝達する.従って,僧帽細胞の突起上のシナプスの分布を明らかにすることは,匂い情報調節を解析する上で必須である.従来,シナプス結合を形態学的に同定するものは高解像度な電子顕微鏡による解析であった.しかし,電子顕微鏡では,観察できる領域は限られ,広範囲の解析を行うのは困難であり,僧帽細胞を厳密に同定することもできない.Vesicular glutamate transporter(VGLUT1)やvesicular GABA transporter(VGAT)などのシナプスマーカーの有用性が最近多くの脳領域で報告されており,これらのマーカーにより電子顕微鏡による解析以上に,嗅球でも信頼性の高いシナプスの定量ができるかもしれない.本研究では,新たなマーカーによる,樹状突起間シナプスの同定の有用性をマウスの嗅球で検討した.まず,嗅球を抗VGLUT1抗体,抗VGAT 抗体で単染色し,電子顕微鏡で観察すると,非対称性シナプス,対称性シナプスのシナプス終末がそれぞれ標識されることが確認できた.次に単一の僧帽細胞をウイルスベクター注入により標識し,抗VGLUT1抗体,抗VGAT 抗体で多重染色して, 僧帽細胞とVGLUT1,VGAT との共存部位を共焦点レーザー顕微鏡で観察した.次いで同部位を電子顕微鏡で同定し,微細構造を解析した.その結果,VGLUT1陽性部位のうち82%に非対称性シナプス,VGAT 陽性部位のうち79% に対称性シナプスが電子顕微鏡で同定でき,VGLUT1,VGAT が,嗅球のシナプスの質的な解析や定量のためのマーカーとして信頼できると結論づけた.また,抗VGLUT1抗体,抗VGAT 抗体で二重染色したものを,高解像度でモンタージュ撮影すると,VGLUT1が外網状層を中心,VGAT が糸球体層に多く分布し,外網状層に中等度分布するなど,新たな知見が得られた.これらの結果は,VGLUT1とVGAT が,シナプスの同定や広範囲の脳領域のシナプスの分布を解析するために有用なマーカーであるということを示している.doi:10.11482/KMJ-J42(2)127 (平成28年8月23日受理)
2016.10.05
Mechanical analysis of contact pressure of Screwless uncemented cup bearings
セメントレスTHA において安定したスクリューレスCup の初期固定を得るには,高い回旋開始時トルク値で初期固定力を確保し,高範囲かつ適切な接触領域の分布を示すことが重要と考える.これまでCup の接触面積がどの程度減少してしまうと,固定力に影響するか力学試験解析した報告は少ない.Cup 摺動部の接触領域を変化させ,実際のヒト寛骨臼の硬さを想定したボーンモデルを作製しフィンの有無が与える影響について力学試験を行った.Cup の辺縁全周が接触するように1mm のアンダーリーミングを行った後に,臼蓋形成不全による骨欠損の有無の影響を考慮し,Cup が臼蓋縁よりはみ出すように骨モデルを10°,20°,30°,40°の角度をつけてカットした骨欠損モデルと,術中の臼蓋に対し再リーミングを想定し1,2,3,6,9mm 偏心したモデルにおいて検討した.骨欠損モデルでは接触面積が10°:94.4%,20°:88.9%,30°:83.3%,40°:78.6%と小さくなり,偏心モデルにおいては1mm:60.4%,2mm:56.7%,3mm:56.2%,6mm:57.8%,9mm:60.4% と6mm 以上の偏心で接触面積は再増加した.最大トルク値では,フィン有りは0°:60.1N/m,10°:58.8N/m,20°:50.2N/m,30°:25.3N/m, 40°:17.4N/m.フィン無しは0°:46.2N/m,10°:40.4N/m,20°:23.5N/m,30°:13.9N/m,40°:7.4N/m であった.フィンの有無に関わらず30°で回旋トルクが著明に低下していた.力学試験においては30°以上において回旋トルク値が極端に低下した.偏心モデルでは2mm 以上で回旋トルクが極端に低下した.結論として,骨との接触面積が減少し,さらにはフィンの掛かりが減少したことが,回旋力低下の要因に大きく影響した. doi:10.11482/KMJ-J42(2)117 (平成28年7月28日受理)