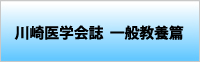2015.02.08
Severe hyperkalemia following ileostomy not colostomy in a patient undergoing chronic hemodialysis
2015.02.04
Impact of systemic heparinization on platelet function in autologous platelet-rich plasma
心臓大血管の手術において術中止血に難渋する場合や大量輸血を要する場合がある.特に血小板製剤は供給量が限られており,自己血貯血,血小板成分貯血の有用性が報告されている.術中自己血小板採取には約90分を要するが,ヘパリンの採取血小板機能への影響は不明であり,採取終了まで人工心肺を開始できないことから,手術時間が延長しているのが現状である.ヘパリンによる自己多血小板血漿(PRP)への影響がなければ,採取と同時に手術の進行が可能となり,手術時間の短縮が期待できる. 今回我々は, 全身麻酔下にブタを用いて, 成分採血装置COMPONENT COLLECTIONSYSTEM(HAEMONETICS 社)による自己血小板採取を行い,ヘパリンがPRP の血小板凝集能に与える影響を検討した.1頭のブタに対し1週間の間隔を置いて2度の採血を行い,1度目はヘパリン非投与群(N 群)とヘパリン投与群(H1群)の採血を行い,2度目はヘパリン投与群のみ(H2群)採血を行った.N 群とH 群で採取した血小板数および血小板凝集能の比較を行った.血小板凝集能はHEMA TRACER 712(MCM 社)にて測定した.本研究は川崎医科大学動物実験委員会の承認を得て行った. データ数はN 群7例,H 群12例(H1群7例,H2群5例)であった.PRP 中の血小板数はN 群で153.6 ± 67.6×104 /μl,H 群で142.8 ± 47.6×104 /μl であり,有意差はなかった(p = 0.6857).また,血小板の最大凝集率はN 群,H 群で凝集惹起物質濃度がADP 2 μM で32.1 ± 9.2,24.1± 13.6%(p = 0.183),ADP 4 μM で44.6 ± 6.4,33.5 ± 13.3%(p = 0.057),Collagen 2 μg/ml で43.4 ± 28.5,28.8 ± 16.4%(p = 0.176)と有意差は認めなかったが,高濃度のADP の場合のみH 群でより低い傾向にあった. 今回の実験ではヘパリン投与前後で採取した自己血小板の凝集能に差は認めず,PRP 中の血小板数および血小板機能はヘパリンの影響は受けないと結論できる.よって,今後は臨床での術中自己血小板採取の有用性について研究を進めていく.doi:10.11482/KMJ-J41(2)143 (平成27年10月5日受理)
2015.02.04
Impact of systemic heparinization on platelet function in autologous platelet-rich plasma
心臓大血管の手術において術中止血に難渋する場合や大量輸血を要する場合がある.特に血小板製剤は供給量が限られており,自己血貯血,血小板成分貯血の有用性が報告されている.術中自己血小板採取には約90分を要するが,ヘパリンの採取血小板機能への影響は不明であり,採取終了まで人工心肺を開始できないことから,手術時間が延長しているのが現状である.ヘパリンによる自己多血小板血漿(PRP)への影響がなければ,採取と同時に手術の進行が可能となり,手術時間の短縮が期待できる. 今回我々は, 全身麻酔下にブタを用いて, 成分採血装置COMPONENT COLLECTIONSYSTEM(HAEMONETICS 社)による自己血小板採取を行い,ヘパリンがPRP の血小板凝集能に与える影響を検討した.1頭のブタに対し1週間の間隔を置いて2度の採血を行い,1度目はヘパリン非投与群(N 群)とヘパリン投与群(H1群)の採血を行い,2度目はヘパリン投与群のみ(H2群)採血を行った.N 群とH 群で採取した血小板数および血小板凝集能の比較を行った.血小板凝集能はHEMA TRACER 712(MCM 社)にて測定した.本研究は川崎医科大学動物実験委員会の承認を得て行った. データ数はN 群7例,H 群12例(H1群7例,H2群5例)であった.PRP 中の血小板数はN 群で153.6 ± 67.6×104 /μl,H 群で142.8 ± 47.6×104 /μl であり,有意差はなかった(p = 0.6857).また,血小板の最大凝集率はN 群,H 群で凝集惹起物質濃度がADP 2 μM で32.1 ± 9.2,24.1± 13.6%(p = 0.183),ADP 4 μM で44.6 ± 6.4,33.5 ± 13.3%(p = 0.057),Collagen 2 μg/ml で43.4 ± 28.5,28.8 ± 16.4%(p = 0.176)と有意差は認めなかったが,高濃度のADP の場合のみH 群でより低い傾向にあった. 今回の実験ではヘパリン投与前後で採取した自己血小板の凝集能に差は認めず,PRP 中の血小板数および血小板機能はヘパリンの影響は受けないと結論できる.よって,今後は臨床での術中自己血小板採取の有用性について研究を進めていく.doi:10.11482/KMJ-J41(2)143 (平成27年10月5日受理)
2015.02.03
Discriminatory ability of trabecular bone score for osteoporotic vertebral compression fractures in elderly Japanese women
海綿骨スコア(TBS)は二重エネルギーX 線吸収測定法(DXA)の画像における各画素の濃度変動を表すテクスチャー指標で,骨強度の決定要因の一つである骨微細構造の簡便な評価法として期待されている.本研究では,日本人高齢女性においてTBS と骨粗鬆症性椎体骨折の関係を調査し,TBS の骨折リスク評価における意義を検討した.研究デザインは後ろ向きの症例対照研究で,脆弱性の椎体骨折の既往を持つ65歳以上の女性76名(平均年齢74.8歳)を年齢を一致させた対照例152名と比較した.椎体骨折の有無は単純X 線画像で確認した.骨代謝に影響を及ぼすような既往歴あるいは服薬歴のある症例は検討対象から除外した.腰椎および大腿骨近位部の骨密度はDXA により測定し,TBS は専用の解析ソフト(TBS iNsight . software v2,Medimaps,Geneva,Switzerland)を利用して求めた.各指標の相関係数はピアソンの相関係数,2群間の比較はMann-Whitney のU 検定,TBS による椎体骨折の有無の識別能はロジスティック回帰分析にて評価した.骨折群の女性ではTBS が腰椎や大腿骨のBMD とともに有意な低値を示した(P<0.001).TBS のオッズ比(OR)は若年成人データの1標準偏差(SD)あたりの減少に対して1.65(95% 信頼区間[CI]=1.27-2.13)であった.TBS は腰椎および大腿骨近位部BMD と中等度の相関を示した(それぞれr=0.443,P<0.001,r=0.291,P<0.001).TBS と椎体骨折との関連は腰椎と大腿骨近位部BMD を補正した後も統計学的に有意であった(OR=1.44, 95%CI=1.07-1.93,P=0.015).さらに,腰椎BMD が正常または骨量減少域の値を示す女性ではTBS が椎体骨折のリスクと有意に関連したのに対し(OR=1.66,95%CI=1.14-2.43,P=0.001),腰椎BMD と椎体骨折の間には有意な関連は認められなかった.これらの結果は,日本人高齢女性においてTBSの低下が椎体骨折のリスクと関連することを示しており,特に骨密度の比較的高い症例での骨折リスク評価における臨床的意義を示唆している.doi:10.11482/KMJ-J41(2)129 (平成27年9月16日受理)
2015.02.02
Arthritis in a patient with Takayasu arteritis
高安動脈炎は全身の大血管に炎症がおこる疾患の1つであり,大動脈及びその主要分枝や肺動脈,冠動脈に閉塞性あるいは拡張病変を来すのが特徴である.初期症状としては,発熱や全身倦怠感などを呈し,その他の症状は障害を受けた血管の部位により異なる.稀には,消化器症状や皮膚症状, 関節症状を呈する事もある. 我々は関節炎を主訴に当院を受診し,後に高安動脈炎と診断された症例を経験した.患者は40歳代女性.左膝及び左足関節痛があり,関節超音波で滑膜炎の所見が認められた.血清学的検査ではリウマトイド因子陰性,抗CCP 抗体陰性であり,未分類型関節炎として少量プレドニゾロンで治療が開始された.メトトレキサートの併用により,関節症状は改善した.しかし,治療開始6ヶ月後,胸背部痛を訴えて受診し,血液検査ではCRP 上昇を認めた.造影CT 検査で,腕頭動脈,左総頚動脈,下行大動脈に壁肥厚と周囲脂肪織濃度の上昇が認められ,高安動脈炎と診断された. 関節リウマチとしては非典型的な関節炎の症例に遭遇した場合には,常に高安動脈炎を含めた,他疾患の可能性を念頭に入れて診療を行う必要がある.doi:10.11482/KMJ-J41(2)121 (平成27年9月1日受理)
2015.02.01
Ultrastructural analysis of synaptic contacts of non-GABAergic interneurons in the rat main olfactory bulb. *
嗅球は比較的少数のニューロン種から構成される明瞭な層構造を持つ脳の領域である.投射ニューロンである僧帽細胞/ 房飾細胞は嗅球の表層の糸球体で匂い情報を受け,細胞体に至る過程で種々の介在ニューロンからの調整を受け,処理された情報を高次中枢へ投射する.情報入力部である糸球体には傍糸球体細胞(JG ニューロン)が多数分布しており,形態的および化学的性質からtype 1 JG ニューロンとtype 2 JG ニューロンの2種の介在ニューロン群に分類される.γ-アミノ酪酸免疫陽性ニューロン(GABA ニューロン)とcalbindin 免疫陽性ニューロン(CB ニューロン)およびcalretinin 免疫陽性ニューロン(CR ニューロン)はそれぞれのtype 1 JG ニューロンとtype 2 JG ニューロンの代表的なニューロン群である.これらのニューロンは対称性シナプスを形成し,抑制性に働くと考えられているが,神経回路内でシナプス形成するニューロンが異なることから,匂い情報の処理過程において異なる働きをしていることが考えられる.また,ラット嗅球のtype 2 JG ニューロンは抑制性の神経伝達物質であるGABA に免疫陰性を示すが,その伝達物質の詳細は不明である.そのため本研究では電子線トモグラフィーによりGABA 免疫陽性ニューロンとGABA 免疫陰性ニューロンが形成するシナプスの詳細な解析を行った.今回解析したシナプスでは,GABA ニューロンとCB ニューロンのシナプス間隙の大きさに有意差が認められ,GABA ニューロンとCB およびCR ニューロン間でシナプス小胞の大きさに有意差がみられた.また,CB ニューロンとCR ニューロンの間においても小胞に形態的な違いがみられた.以上の結果から,同じGABA 免疫陰性ニューロンでも含有する化学物質によってシナプスの形状が異なり,機能的特性が異なることが示唆された. doi:10.11482/KMJ-J41(2)103 (平成27年6月20日受理)