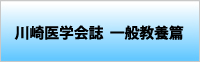2014.02.05
A case report of isolated presacral squamous cell carcinoma developed four years after gastrectomy
2014.02.04
A case of spinal cord infarction *
症例は66歳男性で,30本/ 日の喫煙歴がある.両肩にピリピリしたしびれ感が出現し,その後両上肢と左下肢の動きにくさが出現しその後急激に四肢の筋力が低下し歩行できなくなり,自力で呼吸もできなくなったため緊急入院.気管切開を施行し,人工呼吸器の使用を開始した.頸髄MRI にてC3-6レベルに異常信号域を認め,脊髄梗塞が疑われた. 四肢麻痺(左上下肢は不全麻痺,右上下肢は完全麻痺)を認めた.腱反射は左上下肢および右上肢で消失しており,病的反射はみられなかった.両上肢および臍部以下の温痛覚低下を認めたが,触覚や深部感覚は正常であった.頸髄MRI ではC3-6レベルにT2強調画像で高信号域を認めた.急性の発症であることや頸髄MRI 所見から脊髄梗塞と診断し,オザグレルナトリウム,エダラボン投与とリハビリテーションを開始し,呼吸状態は改善し人工呼吸器から離脱した.左上下肢および右下肢の筋力はやや改善を認めたが,自立歩行できない状態が残存した.右上肢は手指の動きが出てきたが,挙上はできない状態が残存した.脊髄梗塞は稀な疾患であり,その原因としては動脈硬化が多く,その他として大動脈解離,血管奇形,腫瘍塞栓,血管炎,手術や血管造影による医原性,椎間板ヘルニアなどがある.本例では明らかな大動脈解離がなく,血液検査で炎症所見が見られず,頸動脈超音波検査で両総頸動脈のIMT(内膜中膜複合体厚)肥厚を認め,頭部MRI で左椎骨動脈より右椎骨動脈の血管径が細く,頭部MRA の原画像で右椎骨動脈の血流信号が欠如していたことから,原因としては喫煙による動脈硬化が考えられた.急激に発症した四肢麻痺を見た場合には,脊髄梗塞の可能性があることも念頭に置き脊髄MRI を施行すべきと考える.doi:10.11482/KMJ-J40(2)103 (平成26年5月20日受理)
2014.02.03
Ultrastructural analysis of serotonergic synapses in the mouse olfactory bulb *
嗅球は明瞭な層構造を持ち,少数のニューロン種から構成され,そこには豊富な化学物質を含むことがわかっており,脳神経回路の解析に有用な領域である.匂い情報を処理する嗅球は,脳の他領域から複数の遠心性ニューロンによる入力を受けており,この一つがセロトニンを含有するニューロン(セロトニンニューロン)である.セロトニンニューロンは,脳全体に広範囲に分布し様々な脳機能の調節を行っており,嗅球においては非対称性シナプスを形成し,嗅覚情報調節に関わっていると考えられている.しかし,このシナプスについては嗅覚調節機構と共に詳細な解析はなされていない.そこで,本研究ではセロトニンニューロンによるシナプスの微細構造を,免疫電子顕微鏡法と電子線トモグラフィーを用いて解析した.また,非対称性シナプスを示すことから,神経伝達物質としてのグルタミン酸の可能性を検討するため,セロトニンとVGLUT3(vesicular glutamate transporter 3)に対する多重蛍光免疫染色法で解析した.セロトニンニューロンによるシナプスは,多くは球形のシナプス小胞を持つが,扁平なものや有心性小胞も存在した.更に,既知のグルタミン酸作動性ニューロンによる非対称性シナプスと比べて,シナプス後肥厚の厚さの多様性が顕著で,シナプス間隙は狭く,シナプスの直径は小さかった.また,セロトニンニューロンの約半数はVGLUT3免疫陽性であり,神経タンパクを含有する有心性小胞を持っていることから,複数の神経伝達物質を含むことが示唆された.シナプス後肥厚は伝達物質であるグルタミン酸の刺激によって厚くなる.セロトニンニューロンは,グルタミン酸を含む複数の神経伝達物質を持つために,グルタミン酸だけを神経伝達物質として持つニューロンが形成する典型的な非対称性シナプスに比べて,多様性のある非対称性シナプスを形成していると考えられる.doi:10.11482/KMJ-J40(2)89 (平成26年9月22日受理)
2014.02.03
Sulfamethoxazole / Trimethoprim confer no change on the clinical course of Kawasaki disease
2014.02.02
The molecular mechanism by which the short-term intervention of anti-diabetic drugs preserves pancreatic β-cells in db/db mice: comparison of their straightforward effects between early and advanced stage of diabetes *
2型糖尿病の病態進展を抑制する上で,膵β 細胞機能保持は極めて重要な課題である.PPARγ作動薬やインクレチン薬は糖尿病モデル動物のβ 細胞機能保護に働くが,殆どが発症早期の検討であり,病態進展期での検討は十分でない.本研究では肥満糖尿病モデルdb/db マウスを用いて,病態の進展がPioglitazone(PIO)とLiraglutide(LIRA)によるβ 細胞保護効果に及ぼす影響を検討した.早期モデルに7週齢を,進行モデルには16週齢を用い,対照(CTL),PIO, LIRA,併用の4群に分けた.代謝改善による影響を排除し,薬剤の直接的なβ 細胞への効果を検討するため2日間介入とした.またlaser capture microdissection 法を用いて,膵島コア領域の遺伝子発現解析を行った.早期モデルのLIRA 群,進行期の併用群で空腹時血糖の改善傾向をみたが,インスリン値に有意な変動はなかった.進行期モデルでInsulin, GLP-1 受容体遺伝子発現が低下した.分化・増殖に関わるPdx1, NeuroD, ERK1 は早期モデルのみ上昇がみられ,インスリン転写因子Pdx1, NeuroD も同様であった.一方,アポトーシス関連遺伝子Caspase3, Bcl2 の発現は,両モデルでアポトーシス抑制方向に変動した.これらの効果は併用群でより顕著で統計学的に有意であった.脂質合成,炎症,酸化ストレス,小胞体ストレス関連遺伝子発現は,両モデルで変動しなかった.以上より病態早期ではPIO, LIRA は分化・増殖促進とアポトーシス抑制によるβ 細胞保護効果を発揮し,進行期ではその効果は限定的であること,その効果は膵への直接的作用であることが明らかになった.本研究成果は早期からの薬剤介入が糖尿病の病態進展抑制に有効であることを強く示唆する.doi:10.11482/KMJ-J40(2)77 (平成26年8月27日受理)
2014.02.01
Olfactory Brain Circuitry: Analysis of the odor deprivation effect using the naris closed mouse model *
匂いの情報は嗅細胞軸索を介して,嗅球表面の糸球体に入り投射ニューロンの樹状突起とシナプスし,さらに糸球体を構成する様々な神経化学物質を含有するニューロンによって調整される.臨床の場において,慢性副鼻腔炎や鼻茸等で長期間鼻が遮蔽されると症状改善後に嗅覚異常を認めることがある.また,げっ歯類の片鼻閉実験では,糸球体近傍ニューロンのtyrosine hydroxylase(TH)の発現が低下・消失することが知られている.そこで本研究では,マウス及びTH 発現をgreen fluorescent protein( GFP)でモニターした遺伝子改変マウス(TH-GFP マウス)を用い,機能的遮断を施したモデルマウスを作製し,入力遮断によるその他の神経化学物質に対する影響を調べた.方法は,縫合によりマウスの左鼻腔を完全に鼻閉させ,3週間~6ヶ月後に灌流固定し,左右嗅球の連続スライス作製後各種抗体を用いて免疫染色を行った.その結果,これまでの報告と同様3週間の鼻閉モデルマウスでは,鼻閉同側嗅球のTH 発現が著しく低下しており,左鼻腔の入力遮断がなされていたことが示された.また6ヶ月と長期の鼻閉モデルマウスでは,鼻閉同側だけではなく対側嗅球でも著しいTH 発現低下が確認された.TH-GFP マウスでは,TH の発現が低下しているにもかかわらずGFP 発現を維持する細胞が少数見られ,野生型鼻閉モデルマウスでも同様にTH 発現を維持するニューロンが稀に見られた.このようなTH ニューロンは発現低下を示すものよりも比較的大きい細胞体を持つ傾向にあった.以上の結果,TH ニューロンが示す入力遮断に対する反応の多様性は,TH ニューロンが入力刺激に対して異なる電気特性を生じるという我々の最近の研究結果を支持するものと考える.今後,多様性を示すTH ニューロンが匂い入力調節にどのように関わるか解析を進めていきたい.doi:10.11482/KMJ-J40(2)67 (平成26年4月14日受理)