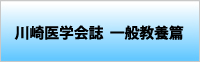2013.01.02
Establishment of an asthma model by sensitization with mite antigen alone in C57BL/6J mice
2013.01.01
Involvement of esophageal motility dysfunction present in several symptoms with pharyngeal or esophageal lesions *
頭頸部領域および食道領域における各種症状に対する食道運動機能の関与を検討した.
2007年9月から2012年6月までに,咽喉頭異常感などの頭頸部領域の症状および嚥下困難感,胸痛,
胸やけなどの食道領域に関連した症状を主訴に,当科を受診した261例(男性138例,女性123例,
平均年齢56.8±17.1才)を対象とし,健康関連QOL(Health Related Quality of Life: HRQL)
の測定と食道内圧検査を施行した.健康関連QOL の検討では,咽喉頭違和感,嚥下困難感,胸
やけ等の各症状を訴えた患者で,身体的QOL,精神的QOL を表すPCS(physical component
summary)あるいはMCS(mental component summary)が低下し,健常者と比較して有意に
QOL の低下を認めた.食道内圧検査による食道運動機能異常は,全対象患者中62.0% に認めた.
各症状別に食道運動機能障害の内訳を見ると,咽喉頭違和感ではIEM(ineffective esophageal
motility)(31.8%),嚥下困難感は食道アカラシア(56.6%),喉のつかえ感は食道アカラシア(35.5%),
胸やけはIEM(39.4%),胸痛は食道アカラシア(50.0%),噫気はIEM(50.0%)を最も多く認め
た.咽喉頭違和感,嚥下困難感,喉のつかえ感,胸やけ,胸痛などの頭頚部および食道症状を有す
るものの,器質的疾患を認めない患者のQOL は障害されており,その病態の一つとして食道運動
機能異常の存在を念頭に置き,診療にあたることが重要である.
(平成24年10月5日受理)
2012.04.09
A case of ileus caused by a Japanese persimmon seed *
症例は80歳代女性.40年前に子宮肉腫と診断され,子宮摘出術と放射線療法を施行された.2年前に腸閉塞のため他院にて保存的加療を施行され軽快した.200X 年9月に頻回の嘔吐が出現したため当院救急外来を受診し,腹部超音波検査(US)で骨盤部の小腸内に半類円形の平滑な境界エコーとそれより直ちに移行する音響陰影を認めた.腹部CT でも同様の位置にhigh density の構造物を認めた.異物による腸閉塞と診断し,イレウス管を挿入した.腸管の減圧に成功したが,食事を開始した翌日に再び腸閉塞の症状が出現した.再度のUS とCT では異物の腸管内での移動は乏しいと思われた.異物の自然排出は困難と考え開腹術を行った.放射線療法の晩期障害と考えられる回腸全体の漿膜の白色調変化と,腸管の軽度硬化と数か所の狭小化を認めた.回腸末端より90cm の部位に固い異物を触れたが同部での縫合リスクは高いと考え,用手的に異物を口側に移動させた後に小腸を縦切開し,異物を摘出した.異物は柿の種であった.US による詳細な観察は種子による腸閉塞の診断および手術の時期判定に有用であった.(平成24年8月29日受理)
2012.04.08
Consideration of bilateral Haglund deformity:A case report *
両側Haglund 変形のため日常生活困難と長距離歩行時痛を来たし,1足に手術を行った症例を報告する.年齢は46歳で,Steffensen & Evensen 角は 90°であった.MRI 上,踵骨アキレス腱附着部にT2強調像で炎症を,またアキレス腱体部にもlongitudinal split 様高信号域を認めた.後踵骨滑液包の炎症は認められなかった.アキレス腱附着部障害は,後方踵骨棘,アキレス腱附着部骨化症,Haglund 病やHaglund 症候群などに分類されているが,病因の同定は困難である.従って各症例に合わせた治療法の選択が重要となる.(平成24年8月13日受理)
2012.04.07
A case of multiple pancreatic metastases from thyroid papillary carcinoma treated by total pancreatectomy *
症例は50歳代の男性で,4年前に甲状腺乳頭癌のため甲状腺全摘術,頸部リンパ節郭清,左迷走神経,左内頚静脈合併切除を施行した.その後,頸部リンパ節再発に対しリンパ節摘出術,131I 内照射,TSH 抑制療法が行われた.甲状腺切除後3年のPET/CT で膵臓への転移を指摘された.急性膵炎を発症したが内科的治療で改善した.甲状腺切除後4年のPET/CT で膵頭部と膵体部の転移巣の増大を認め,また膵尾部にも新たな転移巣を認めた.ERCP では胆管,膵管の狭窄を認め,胆管ステントと膵管ステントを挿入した.しかし十二指腸の狭窄が進行したため,甲状腺切除後4年4か月で膵全摘術を施行した.膵切除後,腹部症状は改善したが,肺転移や脳転移が進行した.膵切除後55週間で死亡した.本症例は多臓器に多発転移を認めたが,甲状腺乳頭癌は比較的集学的治療の有効性が高く予後が期待できるため,QOL 改善目的に膵全摘を行った.(平成24年7月30日受理)
2012.04.05
Choice of surgical treatment for rhegmatogenous retinal detachment complicated with Wagner syndrome *
Wagner 症候群は空虚な硝子体と膜様硝子体混濁,硝子体索状物,進行性の網脈絡膜萎縮や中等度近視などを特徴とする疾患であり,同様の眼所見を有する硝子体網膜変性疾患と異なり全身の異常は伴わない.一般的に常染色体優性遺伝にて発現する.若年時より高率に裂孔原性網膜剥離を合併し,しばしば術後予後不良の事がある.症例は19歳男性で主訴は両眼の飛蚊症であり,初診の3か月後に鋸状縁離断を伴う裂孔原性網膜剥離を発症した.この症例では家族歴は認められなかった.しかし,臨床所見よりWagner 症候群と診断し,強い硝子体牽引を伴った網膜剥離に対し輪状締結術を併施した硝子体手術を施行した.術中復位後,術後再発は認められていない.通常,後部硝子体剥離や黄斑部網膜剥離を伴わない若年者の裂孔原性網膜剥離では,硝子体のタンポナーデ効果を利用して強膜内陥術や輪状締結術を施行する.しかし,この症例の様に硝子体皮質が高度に液化し,硝子体基底部における硝子体牽引が強い場合,輪状締結術を併施した硝子体手術がより効果的であり,これによって硝子体牽引を軽減し裂孔原性網膜剥離の完全復位および再発防止をする事ができた.(平成24年6月27日受理)
2012.04.04
Clinicai Features of Depressive States with Pervasive Developmental Disorders *
抑うつ状態を伴う患者において広汎性発達障害(Pervasive Developmental Disorders;PDD)がどの程度伴い,その場合どのような臨床的特徴があるかについて検討した.DSM-Ⅳ-TR(Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fourth Edition, Text Revision) によって気分障害,適応障害と診断された18歳以上50歳未満の患者のうち,ハミルトンうつ病評価尺度(Hamilton Rating Scale for Depression; HAM-D)において,軽度から中等度の抑うつ状態にある64名を対象として調査した.精神症状の評価はHAM-D,ベックうつ病評価尺度(BeckDepression Inventory; BDI)と精神症状評価尺度(Symptom Checklist-90-Revised; SCL-90-R)を用い,また,PDD の評価は養育者からの発達歴と自己記入式質問紙を用いて評価した. その結果,1)64名のうち,PDD と診断されたのは23名(35.9%)であった.2)HAM-D の総得点において,PDD 群と非PDD 群を比較して,有意な差は認めなかったが,BDI の総得点において,PDD 群が31.3±11,非PDD 群が24±9.9であり,有意にPDD 群の得点が高かった.3)BDI の下位項目では,『悲哀感』,『落涙』,『無価値観』,『食欲の変化』の4項目が,PDD 群で有意に高かった.4)SCL-90-R では,PDD 群が,『強迫症状』と『対人過敏性』と『妄想様観念』の項目の得点が有意に高かった.5)PDD 群のAQ-J の得点では,『注意の切り替え』と『コミュニケーション』の項目で,患者の得点が家族よりも有意に高かった. 医師が客観的に評価するHAM-D に差が認められずに,患者が主観的に評価するBDI が高いということが,PDD 群の抑うつ状態の特徴と考えた. その原因として,患者が内的な体験を人と比較したり,時間経過において比較するのが困難なことや,「全か無か」という考え方などが関与している可能性を考えた.また,抑うつ状態は同程度でも,患者の苦痛感が強い可能性も考えた. PDD 群においては,社会性やコミュニケーションの障害のため,同世代集団から拒絶されたり,孤立したりするという否定的な体験が蓄積しやすく,それがBDI の『無価値観』やSCL-90-R の『対人過敏性』や『妄想様観念』を高めているのではないかと考えた.(平成24年9月25日受理)