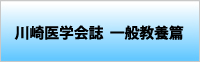2018.05.11
Effects of revisions to the health insurance system on the recovery-phase rehabilitation ward
2018.05.10
Utility of eribulin therapy for patients with metastatic or recurrent breast cancer
エリブリンはタキサンとは異なる作用機序をもつ微小管阻害剤である.海外の第Ⅲ相試験 では,エリブリンの転移・再発乳癌に対する延命効果が示されている.今回,エリブリンの臨床 的な有用性を検討するため,2011年9月から2017年8月に当科でエリブリン療法を行った進行・ 再発乳癌97症例を対象として後方視的に調査した.対象患者の年齢は35 - 81歳(中央値58), performance status は1が最多で64例,Stage Ⅳが5例,再発が92例であった.原発腫瘍のエス トロゲン受容体は陽性が64例,プロゲステロン受容体は陽性が48例,human epidermal growth factor receptor 2は陰性が78例であった.前化学療法のレジメン数は0 - 9(中央値2), 臓器転 移ありが69例,肝転移ありが40例,エリブリン療法の実施サイクル数は1 - 12回(中央値3.5), 観察期間は1 - 55か月(中央値10),有害事象による中止例は10例であった.最大治療効果は,完 全奏効が0例,部分奏効が1例,長期安定が27例,安定が16例,進行が42例,不明・評価不能が 11例であった. 臨床的有効率(奏効率+長期安定率)は29% であった.Time-to-treatment failure (TTF) は0 - 178週間(中央値13),治療開始後全生存期間は0 - 55か月(中央値15.5)であった. 好中球減少症はグレード1が最多で61例,非血液毒性は嘔気が7例,肝機能障害が6例,末梢神 経障害が5例,間質性肺炎が3例などであった.良好なTTF の予測因子は,単変量解析で「臓器転 移なし」(P = 0.0356)が同定された.良好な治療開始後生存の予測因子は,多変量解析にて「臨 床的有効性あり」(P = 0.0008)と「PS が0か1」(P < 0.0001)が同定された.エリブリン療法は, 奏効率は低かったが,本療法は,約30% の症例に臨床的有効性をもたらし,生存期間の延長に寄 与する可能性がある. doi:10.11482/KMJ-J44(1)71 (平成30年3月6日受理)
2018.05.10
A Case of Hypokalemic Rhabdomyolysis induced by a Chinese herbal medicine and a loop diuretic agent
症例は92歳,女性.近医で高血圧や認知症で通院加療中であった.下肢の疼痛に対し,芍薬甘草湯が処方されていた.入院4か月前から下肢の浮腫が出現したためにループ利尿薬の内服が開始された.入院10日前の血液検査で血清カリウム値2.1 mmol/L と低カリウム血症であったために芍薬甘草湯とループ利尿薬の休薬を指示し,カリウム製剤の内服が開始となっていた.入院当日の朝、自宅内を歩行中に転倒し動けなくなったところを近隣の人に発見され当院へ救急搬送となった.受診時,著明な低カリウム血症(1.8 mmol/L),CK 3.612 U/L から低カリウム血症による横紋筋融解症と診断し,補液とカリウム補正を開始した.入院時の検査で低レニン・低アルドステロン血症,尿中カリウム排泄亢進を認めた.甘草を含有する芍薬甘草湯による偽性アルドステロン症と診断し,同剤の中止とカリウム補正によって入院10日目にほぼ正常化した.高齢者において,漢方薬は比較的副作用が少ないことから処方される機会が多い.しかし,高齢者では多数の内服薬が処方されることが多く,各薬剤の服用状況や副作用,それらの相互作用について注意する必要があると考えられる. doi:10.11482/KMJ-J44(1)65 (平成30年3月8日受理)
2018.02.08
Multiple bone metastases of plasmacytoid bladder carcinoma that was morphologically difficult to distinguish from myeloma cells
尿路上皮癌には,腫瘍細胞が形質細胞に酷似した形態を呈することがある.今回,形態学的に骨髄腫細胞との鑑別に苦慮したplasmacytoid な形態を示した膀胱癌の骨髄転移の一例を経験したので報告する. 症例は80歳代男性で,20XX 年10月に蛋白尿と腎機能障害が出現し,精査にて多発性骨髄腫(IgG-λ),ISS Ⅱ期と診断され,BD 療法(bortezomib+dexamethasone)を開始した.効果は良好で,3コース施行後にはVGPR(very good partial response)に到達した.20XX +1年2月間歇的に認めていた血尿の精査を行い,細胞診や膀胱鏡検査から膀胱癌の併発を確認した.骨髄腫治療は中断し,膀胱癌治療を優先した.PET/CT 検査ではリンパ節やその他臓器への転移は認めず,6月に膀胱全摘術が施行された.術後は経過良好であったため,全身状態の回復を待ち,骨髄腫治療を再開する予定であった.しかし,9月末頃から腰痛が出現し,10月には腰痛の増強を認めたため再度PET/CT 検査を施行したところ,多発する骨髄病変を認めた.骨髄腫の増悪を疑い骨髄検査を施行した.骨髄穿刺塗沫標本では,形質細胞様の異形細胞を多数認め,骨髄腫の増悪を推測させる所見であった.しかし同時に施行された骨髄腫関連検査では,IgG やその他の免疫グロブリンは正常であり,蛋白分画や免疫固定法でもM 蛋白は検出されなかった.骨髄生検の病理組織学的検査の結果,形質細胞様の異形細胞は尿路上皮系の腫瘍細胞であり,膀胱癌の骨転移と診断された.PET/CT 検査での多発骨髄病変は,多発性骨髄腫の増悪ではなく,膀胱癌の多発骨転移であった. 膀胱全摘後の再発は,遠隔転移が20~50% と遠隔転移が多く,遠隔転移部位として骨,リンパ節,肺,肝の順に多いと報告されている.そのため,骨髄塗抹標本検鏡の際,遭遇する可能性があり,骨髄腫細胞と見誤らないためには,免疫染色を含めた組織学的な検討,血清・尿の蛋白解析が必須と考えられた.
2018.02.07
Two cases of cryptococcal meningitis developing as a result of CD4 lymphocytopenia
クリプトコッカス感染症はCryptococcus neoformans による真菌感染症であり,免疫不全患者に発症しやすい.今回,我々はCD4リンパ球減少を認め,クリプトコッカス髄膜炎を発症した2例を経験したので報告する.症例1は,40歳代男性で不明熱のため受診した.血液検査でリンパ球930/μL,髄膜刺激症状はなかったが,髄液検査にてクリプトコッカス菌体が検出され,血液培養からも検出された.CD4 72.5/μL と低値であり,HIV 抗体陽性であった.クリプトコッカス髄膜炎を発症したAIDS 患者と診断した.症例2は,20歳代女性で不明熱のため受診した.血液検査でリンパ球510/μL,髄膜刺激症状はなかったが,髄液検査にてクリプトコッカス菌体が検出され,血液培養からも検出された.CD4 19.4/μL と低値であったが,HIV 抗体陰性で原発性免疫不全症や他の免疫不全となる原因は認められなかった.Idiopathic CD4 lymphocytopenia(ICL)に発症したクリプトコッカス髄膜炎と診断した.AIDS とICL がそれぞれ原因となったクリプトコッカス髄膜炎であった.前者での本症併発は2.4 %,後者での併発は19.7 % と報告されている.HIV非感染のクリプトコッカス髄膜炎をみた際にはICL によるCD4リンパ球減少症を考える必要がある.死に至ることもまれではないクリプトコッカス髄膜炎であるが,治療が奏効し1年以上経過しているため報告する.
2018.02.06
Gastric Wall Abscess in Aberrant Pancreas Treated with Endoscopic Ultrasound-guided Fine Needle Drainage: A Case Report
症例は30歳代女性.3日前から心窩部痛が出現し,徐々に増悪してきたため当院を受診した.血液検査でWBC 15,120/μl,CRP 2.95mg/dl と炎症反応上昇を認め,腹部超音波検査で胃幽門前庭部前壁に約3.5cm の粘膜下腫瘍様隆起を認めた.腫瘍内部はechogenic particles の混在する液体の貯留を認めた.腹部造影CT 検査では,胃前庭部から胃体部前壁にリング状の造影効果を伴う著明な壁肥厚を認めた.以上より胃壁膿瘍と診断した.胃前庭部前壁の弾性硬のやや発赤した粘膜下腫瘍様隆起に対して,超音波内視鏡下穿刺術(EUS-FNA)を行った.粘稠な白色液体の流出を認め,膿瘍を示唆する所見であった.絶食・点滴・抗生剤投与による保存的加療を施行後,速やかに腹部症状は消失し,EUS-FNA 施行後5日目に退院した.4か月後,病変は上部内視鏡検査で頂部に陥凹を有する腫瘍に形態変化を認め,さらに縮小傾向であった.また,腹部超音波検査では粘膜下層内に約5mm 大の嚢胞性領域とそれに接する約4mm 大の境界不明瞭な低エコー域,不整な固有筋層の肥厚を認め,胃迷入膵の所見であった.以上より,胃壁膿瘍を合併した胃迷入膵と診断した.現在,再発なく当科で経過観察中である.胃壁膿瘍を合併した胃迷入膵の報告は非常に稀であり,貴重な症例と考えられた.
2018.02.05
A case of reversible cerebral vasoconstriction syndrome
可逆性脳血管攣縮症候群(reversible cerebral vasoconstriction syndrome: RCVS)は,雷鳴頭痛で発症し経過中に可逆性の多発性脳血管攣縮を認めることを特徴とする比較的新しい疾患概念である.発症時における雷鳴頭痛はほぼ必発の症状といえ,救急医療の現場ではくも膜下出血を始めとした重篤で緊急の対処を必要とする疾患との鑑別が重要となるが,雷鳴頭痛をきたしうる疾患の一つとしてRCVS の認知度は未だ高いとは言えない.今回,雷鳴頭痛で発症し典型的な経過をたどった症例を経験したので報告する.患者は50歳女性で,電話で相手に謝罪をしていた時に後頸部に突然激痛が出現し,痛みはすぐに頭部全体に拡がり持続した.くも膜下出血を含む頭蓋内疾患について精査したが発症当初には雷鳴頭痛の原因は明らかでなかった.発症3日目と5日目にも1回ずつ雷鳴頭痛を認め,原因としてRCVS を疑いロメリジンの投与を始めたところ,発症6日目以降頭痛は軽快消失し以後再発を認めなかった.発症8日目の頭部MR angiography(MRA)で脳主幹動脈が複数個所で狭小化している所見がみられ,これらは発症から8週後には正常化し,RCVS に矛盾しない経過であった.この特徴的な血管攣縮所見は特にMRA では発症初期には認めないことが多く,本症例においても診断確定に苦慮した.雷鳴頭痛を呈する症例では可逆性脳血管攣縮症候群も鑑別診断に加え診療する必要がある.